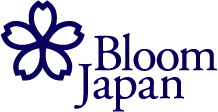鶴琳窯 林 英樹氏 インタビュー
独自の色彩と技法で魅せる美濃焼の世界
プロフィール/陶歴
(はやし・ひでき)
1974年岐阜県土岐市駄知町生まれ。1996年、名城大学理工学部建築学科を卒業後、大手ゼネコンに就職したのち地元の駄知へ帰郷。多治見県立多治見工業高校専攻科陶磁科学芸術科で陶芸を学び、2001年卒業。2014年に美濃陶芸協会へ入会、2018年に土岐市からの要請よりイタリアのファエンツァへ招へい。2023年に第9回美濃陶磁育成智子賞を受賞。実家である「鶴琳窯」にて作陶に励んでいる。美濃陶芸協会理事。
陶歴
- 2014年
- 美濃陶芸協会へ入会
- 2018年
- 土岐市からの要請よりイタリアのファエンツァへ招へい
- 2023年
- 第9回美濃陶磁育成智子賞受賞
カラフルな釉薬が彩る器たち
レッド、イエロー、トルコ、ピンク、パープル…。カラフルな釉薬を施した碗や皿、鉢が並ぶ鶴琳窯(かくりんがま)。
色名をカタカナで表記するのは、「その方が分かりやすいのでは」という林英樹さんの心配りから。使い込まれた棚や台、箪笥に陳列された器たちは、まるで海外のガレージやアートギャラリーを思わせる雰囲気です。
『ほっとできる温もり』を感じられる器を提供する林英樹さんを訪ねました。


「鶴琳窯」ではギャラリーのような工房で作品を見ることができる(要事前確認)
美濃焼の産地・土岐市で育まれた陶芸のルーツ
岐阜県南東部に位置する美濃焼の産地、土岐市。特に“どんぶりの町”と称される駄知町では、陶磁器生産が地場産業として根付いています。
林英樹さんは、製陶業を営む父のもとに生まれ、幼少期から陶器が身近な環境で育ちました。
小・中学校には校内に窯があり、陶芸の授業も実施。学生時代のアルバイト先も製陶所だったため、陶器はあまりにも日常的な存在だったといいます。
しかし、大量生産が主流だった時代、父が朝から晩まで四立米の窯で焼き続ける姿を見て、「家業を継ぐことは考えなかった」と語ります。厳しい世界であることを、子どもながらに理解していたのです。

建築業から陶芸の世界へ
ものづくりが好きだった英樹さんは、建築にも興味を持ち、建築学科を卒業後、東京の大手ゼネコンに就職。
しかし、設計の図面で線を引いても“建物をつくっている”という実感が得られず、違和感を覚えていました。より直接的に建築に関わるため、小規模な建築会社への転職を考え、地元に戻ります。
そんな中、友人に誘われて訪れた陶芸教室で、粘土に触れる感覚に心地よさを感じました。作陶中は「何も考えなくて良かった」ほどに没頭し、自らの手で形を生み出す楽しさを実感。
実家には材料も窯も揃っていたことから、どんどん陶芸にのめり込んでいったと振り返ります。

陶磁科学芸術科での学びと転機
より深く陶芸を学びたいと考え、岐阜県立多治見工業高校専攻科 陶磁科学芸術科へ入学。
社会人経験者や定年後に学ぶ人、遠方からの学生など、多様な背景を持つクラスメートと過ごした2年間は、大きな刺激となりました。
「10代・20代の若者たちがものづくりに没頭する姿を羨ましく思った」と話す英樹さん。自身は“何時までに何個生産”といった意識が抜けず、生産性を考えてしまうことに気づきました。
卒業後は4代目として家業を継ぎ、大量生産から「少数・多品種」へとシフト。また、社名『カク林製陶所』に『鶴琳』を加え、窯元として趣向を凝らした生活雑器を制作する体制を確立しました。

建築の視点を活かした独自の作風
林英樹さんの作品は、“印象的な柄と色使いの組み合わせ”が特徴。
アルファベットのような文様、大胆な直線、幾何学模様が独自のバランスで配置され、こだわりの釉薬と融合し、和洋どちらの要素も感じさせるアートな印象を与えます。
独自の技法『線刻』には、建築業界で培った経験が生きています。図面を描いていた時は、シャープな線が引けているかを意識していたとのこと。粘土の柔らかい側面に、切れの良い線画を施すために、英樹さんは道具にも工夫を凝らします。
デザインナイフや彫刻刀は、好みの線が描けるように先端を削ってアレンジ。また、連続した細い線を描くためには、何本もの裁縫針を小さな板の上に横に並べテープで巻いたものを自作。ポンス(丸い穴を開けるための陶芸道具)は切断した傘の骨を尖らせて作りました。それらの線刻と、ピーコン穴(コンクリートの型枠を取り除いた跡)からアイデアを得た丸い凹凸を組み合わせ、一目でそれと分かる華やかな柄が出来上がるのです。
「作品に向変数と、線やデコボコなど好きなものがつい出てしまう」と、にこやかに英樹さんはおっしゃいます。こうした独自のアプローチにより、一目でそれと分かる個性的な柄が生まれます。

一つずつ丁寧に特徴のある紋様が施されている
彩り豊かな釉薬と青白彩へのこだわり
陶芸作品の中では珍しい鮮やかな赤や黄色を取り入れる理由は、「他の作品を引き立てる差し色として計算されている」から。
釉薬の調合について「科学であり無限」と語る英樹さん。現在では手に入らない材料や再現できない色合いもあるものの、それも「巡り合わせ」と捉えています。
中でも、「透明度のあるブルー、青白彩(せいはくさい)を突き詰めていきたい」との想いが強いそうです。

ファッションと作陶に共通する美意識
英樹さんのファッションにもこだわりが表れています。
取材当日も、袖元や襟、ボタンまでデザインにこだわったコムデギャルソンのジャケットを着用。デザイナーの川久保玲氏を深く敬愛していると語り、自己表現としてのファッションと作陶に共通する意識があることを伺わせます。
幼少期から絵画教室に通い、現在も桐箱に自ら筆を入れるなど、美意識の高さは作品にも投影されています。
「器を手に取られた方が、私の名前を知らなくても認識してもらえるような作品を意識している」とおっしゃる英樹さん。アルファベットにも見える柄についてはアルファベットの子音から発想を得たのだそう。連続模様的に“何となく描いている風“にするため、「角度や配置など色々と試して今のバランスに辿り着いた」そうです。中にはご自身の名前を現すHDKを表す線もあるとのこと。主張しないように崩してあるそうですが「自己顕示欲の現れです」と笑って語られていました。

「陶芸家とは違う」—林英樹さんの哲学
「自分は陶芸家とは違う」と語る英樹さん。
陶芸は観賞用ではなく、“使ってもらうもの”。そのため、芸術とは異なると考えています。
製陶業と陶芸、家業と作陶。そのバランスを模索しながら、自身の生き方と向き合う日々。
「手に取ってくれた人の生活に、何かホッとできるものを届けたい」という想いが、林英樹さんの作品には込められています。
(2025年2月、インタビュー:志村 知夏)
information
鶴琳窯
〒509-5401 岐阜県土岐市駄知町1919