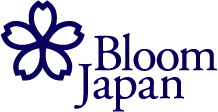水晶窯 細川令子氏インタビュー
磁器への転向と独自技法が生み出す“霞白磁”の美
プロフィール/陶歴
(ほそかわ・れいこ)
- 1959年
- 神奈川県鎌倉市生まれ
- 1981年
- 武蔵野美術短期大学陶磁器デザイン科卒業
- 1983年
- 多治見市陶磁器意匠研究所卒業後、陶磁器商社にデザイナーとして就職
愛知県瀬戸市の陶芸家 加藤釥氏・令吉氏に師事 - 1995年
- 独立、岐阜県土岐市泉町に『水晶窯』を築窯
美濃陶芸協会理事 土岐市陶芸協会員 日展会友 日工会員 - 1997年
- 日展初入選(以降11回入選…2024年現在)
- 1998年
- 朝日陶芸展入選
- 2012年
- 高岡クラフト展入選
- 2014年
- 現代茶陶展奨励賞受賞
- 2015年
- 美濃陶芸展中日奨励賞受賞
- 2016年
- 萩大賞展Ⅳ 入選
- 2017年
- 女流陶芸T氏賞受賞
- 2021年
- 岐阜県伝統文化継承者表彰受賞
- 2023年
- 日展東海CBC賞受賞
第41回卓男賞受賞 - 2024年
- 陶美展入選
JR土岐市駅から北へ10分ほどの静かな高台。道路から敷地を覗くと、庭の植木の根元や玄関先には色や形の異なるオブジェが無造作に置かれています。室内に一歩足を踏み入れると、たくさんの“白”が目に飛び込んできました。小さな器から、迫力を感じる大きさのオブジェまで、作品が並ぶ陶磁器作家 細川令子さんの工房を訪ねました。
陶芸との出会い、独立までの道のり
令子さんの陶芸との出会いは高校時代。お姉さんの陶芸体験に付き添い、体験したのが初めてとのこと。最初は月に2回、手びねりで小鉢を作る程度でしたが、土を触る感触や作品が焼き上がる瞬間の“わくわく感”に魅了され、「もっとやりたい」という気持ちが芽生えたそうです。
武蔵野美術短期大学 陶磁器デザイン科に進学され、クラフトデザイン的な少量・手作りの器を学びました。在学中、自由制作にて陶器だけでなく磁器にも触れる機会があり、その難しさと魅力を実感したそうです。
令子さんは大学卒業後も伝統的な陶芸も学びたいとの気持ちから、信楽・京都・瀬戸など、日本各地の産地や学校を実際に訪れました。その中でも「一番ウェルカムな環境だった」と振り返られ、多治見市陶磁器意匠研究所に進学します。
その当時、東美濃地方では集団就職の受け入れから他地域出身者でも受け入れる土壌があり、器以外にも建材など多分野の窯業が集まる美濃焼は、技術的にも多くを有する環境でした。その多様性を感じて移住した当時の決心に間違いは無かったと、令子さんは振り返ります。
在学の2年間で陶磁器の知識や技術を身に付け、卒業後に多治見市内の陶磁器商社にデザイナーとして就職しました。その後、自身の作品制作に専念する道を辿ります。
令子さんが愛知県瀬戸市の加藤釥氏・令吉氏に師事したのは結婚後、お子さんがまだ1歳を超えた頃。「夫には結婚後も陶芸を続けることに理解してもらっていましたが、子供がまだ小さく家事に保育園に作陶にと記憶がないほど忙しかった」と当時を振り返られます。
そのような中、大型の作品にも挑戦し公募展に出すことを勧められます。オブジェは造るものではなく「見るものと思っていた」という令子さん。戸惑いながらも作品を少しずつ大きくしていき、公募展で入選・受賞を得られるようになり独立を決意し、地名に因んだ『水晶窯』を岐阜県土岐市に築窯します。

磁器への転向
もともと磁器への憧れがあった令子さんは、2010年から本格的に磁器に取り組み始めます。
それまでに陶器の制作では自身の思う形を作れるように技術を身につけていましたが、「陶器制作を続けていっても、自分の中に新たな発見がない」と感じたそうです。いつかは磁器に向き合いたいという長年の想いと、50歳を迎え「死ぬまでには満足いく磁器の作品を完成させたい、今ならまだ足掻き甲斐がある」と、磁器への完全移行を決断しました。
しかし磁器は、技術的に陶器よりも難しく、試行錯誤の連続でした。
粘土質の土を素材とする陶器に対し、磁器は粉末にした石を粘土状にして作る為、轆轤(ろくろ)作業で崩れや変形が起こりやすくなります。また焼成温度が高い為、低い温度なら耐えられる形も高温では崩れやすくなるそうです。また陶器の仕上がりとは異なる予想外の課題も多々ある中でも、「どうしても磁器で作品を作りたい」という強い想いから、令子さんは独自の技法を模索していきます。
大型のオブジェ制作では、全ての工程を手捻りで行うと手跡がついてしまい、仕上がりが美しくありません。また轆轤だけでは崩れやすく、これもまた大物には向いていません。鋳込み成形では作品自体が重くなるため腕力が足りず、「そもそも好みではない」と令子さん。試行錯誤を重ね、作品の土台となる下の部分を轆轤で引いた後に、上部は手仕事で粘土を紐状に付け足す技法を生み出し、冷たい印象を与えがちな磁器の作品に“揺らぎのある柔らかさ”も与えます。

磁器制作の工程
焼成後の仕上げにもこだわりがあり、『霞白磁(かすみはくじ)』では一種類の釉薬の濃淡を利用し、斑な文様のようにも見える独特の表情を作ります。また、小さめの器の見込みの茶だまり(内側の底)にブルーやグリーンのひび割れたような透き通る輝きが溜まる様は、『玻璃釉(はりゆう)』というガラス質の釉薬を重ねて出しています。これらの釉薬は市販のものをそのまま使うのではなく、オリジナルの調合を加えて独自の色合いを生み出しているそうです。
修正がきかない磁器の制作では、イメージを形にするために「落書きのような」デッサンを何枚も描き、2次元を3次元にするためには粘土で小さな模型を作ります。いろいろと試してデザインが固まってから実際の制作に入る為、「作る前の方が時間がかかる」と令子さんはおっしゃいます。
工房には令子さん自作の採寸用トンボがたくさん並び、ゴムベラ、木製のこて、超硬カンナなど、段階に応じた成形の為の小ぶりな道具が数多くあります。他にも、サンドペーパ、ペットボトルのキャップ、金網状のスポンジ等、陶芸用でなくても使えそうなものは何でも試してみるそうです。

作風とインスピレーション
令子さんの作品は自然の美しさをモチーフにしたものが多く、特に“清潔感や品格のある佇まい”を大切にしています。例えば、翡翠(カワセミ)が見せる一瞬のシルエットや、水芙蓉(ハス)の茎が水面から伸びる様や、葉についた水滴の輝きといった、実際の鳥や植物をそのまま形にするのではなく、「その場の空気感や雰囲気」を抽象的に表現しているのです。散歩中に見つけた美しい風景や、水面の揺らぎ、またご自身で「活字中毒」とおっしゃるほど好きな読書などがインスピレーションの源になっています。
磁器に移行後の10年間は思うような作品が作れなく、公募展でもなかなか入選できないこともあり苦しい時期でもあったそうです。「こんなに手間をかけて自分の作品に辿り着けるのか?」と思うこともあったとのこと。しかし、作品作りの楽しさ、少しずつ表情が違う面白さからは離れられなかったとおっしゃいます。
作品に挑み続けたからこそ、公募展での受賞のみならず、美濃陶芸永年保存事業作品選定・岐阜県伝統文化継承者表彰受賞など、令子さんの作家活動に対する高い評価へとつながりました。審査員を務める尊敬する作家から自身の作品を認められ、特に大きな励みになったと穏やかに令子さんは語ります。

今後の展望
令子さんは、「磁器で作るのにふさわしい色と形を追求したい」と話します。白磁・青白磁にこだわり、その良さを生かす、紫色・桜色・墨色など新たな色彩の釉薬を試し、その色調に合う形を模索している最中。単なる色違いではなく、「色と形が調和する作品」を目指しています。また、引き続き公募展への出品を続けるとともに、個展の開催にも意欲を見せています。今後も、磁器の持つ“本質的な美しさ”を自分が納得できるまで追求し、「100歳まで続けたい」と語る令子さんの作品は、さらなる進化を遂げていくことでしょう。
(2025年3月、インタビュー:志村 知夏)
information
水晶窯
〒509-5142 岐阜県土岐市泉町久尻1417-111