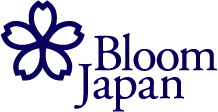大雲窯 加藤三英氏 インタビュー
黄瀬戸と瀬戸黒に魅せられて
陶芸への挑戦と美濃焼の未来
プロフィール/陶歴
(かとう・みつひで)
昭和43年岐阜県土岐市生まれ。平成元年、京都芸術短期大学・陶芸科を卒業。京都府立陶工高等技術専門校へ進み、平成3年に修了する。平成7年に土岐市に戻り、窯元としての製造業に務めながら、作陶を続ける。公益社団法人美濃陶芸協会の副会長として展覧会事業の責任者を務め、美濃陶芸の発展に貢献したことなども評価された。
(受賞歴 2025年現在)
平成8年美濃陶芸展・中日奨励賞受賞、平成13年日本新工芸展・東京都知事賞受賞、平成17年美濃陶芸永年保存品に選定される。平成24年庄六賞茶盌展・銀賞受賞、平成27年第1回美濃陶磁育成 智子賞・受賞を受賞、令和6年第42回卓男賞受賞。
岐阜県土岐市の中心部から少し離れ、製陶業や陶器商の建物がならぶ下石(おろし)町。幹線道路からすこし脇に入って坂道を上がり、小高い山を登りきる手前に大雲窯があります。工房にお邪魔して、お話を伺いました。工房に入る手前の部屋には、古い母屋をリフォームされた際に廃棄予定だった扉をリメイクした、存在感のあるテーブルが置かれており、その印象的な姿が目を引きます。部屋には多くのマグカップが並んでいて、製陶業としてもご活躍されていることが伝わります。また、三英さんの奥様手作りの多肉植物の寄せ植えも並べられ、落ち着いた空間に彩りを添えています。個展を目前に控えたお忙しい中、貴重なお話をお聞かせいただきました。
京都での作陶と黄瀬戸への出会い
三英さんの作陶の原点は京都にあります。芸術大学と訓練校で陶芸を学び、陶芸に関わる仕事をしながら、積極的に展覧会へ出展してきました。奥様との出会いも、陶芸をされていたお二人が8年間ほど京都に滞在していた間のことです。出身地である美濃の技法が作品に一つもないことを指摘されたことをきっかけに、主に灰釉を手掛けていた流れから黄瀬戸も手掛けるようになったそうです。
出展予定の黄瀬戸の壺を見せてくださいました。淡い黄色の肌に、所々青緑の「胆礬(たんぱん)」を用いた装飾が施されています。鉱物を粉にして素地に埋め込んで焼くと、緑色に焼き上がり、アクセントになるそうですが、三英さんは「合成の化学硫酸物は不純物がないため、緑色が綺麗すぎる」とおっしゃいます。「今回たまたま天然物が手に入ったから」と、碧く輝く小さな塊の鉱物が入った袋を手に取られました。
「黄瀬戸の昔ながらのぼてっとした落ち感に、青黒いような黒緑が出て、思い通りの仕上がりになった」と語る三英さんですが、近年、灰と長石の調合だけでは黄瀬戸の特徴的な黄色が出にくくなってきたとのこと。釉薬に含まれる微妙な鉄分で黄色味が出るそうですが、最近の灰にはその鉄分が少なくなってきているそうです。

独自技法への挑戦と瀬戸黒へのこだわり
三英さんは、昔ながらの色合いが出る質の良い原料が年々減ってきていることを案じています。1種類の灰でも黄瀬戸の黄色を出すことはできるそうですが、三英さんはあえて土灰や樫灰など3種類の灰を混ぜ、さらに数%の鉄を加えて釉薬を手作りしています。「いずれ手に入らなくなった時に困らないように」と、もしもの時のための対策を今から講じているのです。
また、使用する樫灰については和歌山県まで足を運び、2トンもの赤松の薪を仕入れて灰にするというこだわりを持っています。脂気のある針葉樹の硬い木が良い薪になるそうですが、近年では赤松の薪も手に入りにくくなっているそうです。2トンの薪が暖炉で燃やされると、6キロの灰になり、さらに灰汁を取り除くと2キロ enthusiasmにまで減ってしまうとのことです。それでも、直接触れると手が荒れてしまうほど灰汁が強い、良質な灰ができ、その灰を大切に黄瀬戸に使用しているそうです。
こだわりを持って取り組んでいるのは瀬戸黒においても同じです。かつて加藤孝造氏に師事していた頃は、窯焚きの際に手伝いながら、瀬戸黒に強い思いを抱かれたそうです。「同じものを作っても面白くない」との理由から、従来の高温の器を水で急冷する技法(引出黒)ではなく、「炭化黒」という技法をアレンジして、籾殻に密閉して黒を出す方法を採用。また、銀彩を施すことでオリジナリティーあふれる作品を作り上げています。
独創性を追求し、より良い作品作りのために常に努力を惜しまない三英さんですが、まだ到達すべき境地があると感じているようです。元来、茶碗のみが作られていたとされる瀬戸黒ですが、孝造氏の作品は、そのサイズを問わず、特に写真に撮った際に現れる色彩の素晴らしさが際立つといいます。その違いを考えた時、三英さんは「答えはやはり薪にある」と語ります。登り窯や穴窯で温度や湿度を調整しながら薪を使って焼くことで、自然と灰が飛び、茶碗の一部や全体に付着し、「かいらぎ」を生じさせるのです。ガス窯で焼成するものとは全く異なる仕上がりになるそうです。そのため、三英さんにはいつか薪窯を作り、そこで焼き物をしたいという夢があるとのことです。

志野への憧れと伝統技術の未来
さらに、まだ手掛けていない「志野」にもいずれ挑戦したいとおっしゃいますが、釉薬の原料となる長石が手に入らないことを嘆かれています。この美濃の土地に窯を持ち、美濃焼に欠かせない粘土や土はまだ手に入るものの、天然の鉱物や薪の不足は深刻であり、それは薪窯で焼かれる伝統的な美濃焼の存続にも関わると、三英さんは非常に危機感を抱いていらっしゃいます。

資源の不足だけでなく、伝統技術の継承においても同じ懸念があるようです。「作ってもらった釉薬を買ってきて、電気やガスの窯で焼く陶作家ばかりになってしまったら、伝統的な技法は途絶えてしまうのでは…」と。ご自身が若手作家だった頃を振り返り、工芸会や陶芸協会に所属することで、世代を超えた人間関係の中で、先輩方にあらゆることを教わる機会があったと三英さんは語ります。そうして昔ながらの技術や技法、経験を自分のものにしていったのだと。三英さんの作家人生は「人に恵まれて」歩んできたようです。現代のSNSを使った横のつながりだけでは得られない、縦のつながりから学んだことが、三英さんの陶芸に生かされています。『後進の育成』を、60歳を目前とした現在のご自身の使命と感じていらっしゃるように思いました。

また、灰について伺っていた際に、非常に興味深いお話を聞かせてくださいました。昔の京都では、かまどで煮炊きに使った炭や灰を業者が回収し、それを染物屋が染色の際の灰汁抜きに使用し、その後また回収して次は陶器屋に渡すという、循環型のシステムがあったそうです。何と、今で言うSDGsのような仕組みが既に存在していたのです。
三英さんが大先輩や先輩方から学んだ美濃陶芸の伝統技術や技法が、三英さんを通じて現代に引き継がれ、それが若手作家へと伝えられ継承されていく。そんな技術の循環が続く美濃焼の未来を想像しました。
(2024年8月、インタビュー:志村 知夏)
information
大雲窯
〒509-5202 岐阜県土岐市下石町2549-1