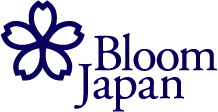木村元氏 インタビュー
土と釉薬が織りなす独自の世界・美濃焼に込める想い
プロフィール/陶歴
(きむら・はじめ)
1980年、岐阜県土岐市に生まれる。愛知学院大学経営学部を卒業後、多治見市陶磁器意匠研究所デザインコースを修了。卒業後は美濃焼伝統産業会館で作陶指導員として勤務。その後、代々続く窯元を継ぎ、陶芸家としての活動を本格的に開始。伝統的な技法をベースに、桃山時代の黄瀬戸に魅せられ、地元岐阜の原料を活用した作品づくりを行う。特に「自然灰を用いたしっとりとした質感」と「釉薬の流れと動き」を重視した作品は、多くの入選、賞を受賞しており、高い評価を得ている。(公社)美濃陶芸協会 理事、(公社)日本工芸会 会員(東海支部所属)。
(受賞歴・活動歴 2025年現在)
美濃茶盌展や東海伝統工芸展などで数多くの入選。国際陶磁器フェスティバルや国内外の陶芸イベントに参加。イタリア・ファエンツァ市での世界的陶器イベント「ARGILLA ITALIA」に土岐市代表として派遣、書家とのコラボレーション作品制作。作品が国際陶磁器博物館(MIC)に寄贈される。
岐阜県土岐市で陶芸活動を行う木村元さんは、美濃焼の伝統を大切にしながら、新しい可能性にも挑戦しています。その根底には、六代続く家業を引き継ぐ覚悟と、日々の努力から得た深い知見があります。今回、木村さんの工房を訪れ、創作への思いや日々の取り組みについてお話を伺いました。
地方の自然素材を生かした木村さんの焼き物作り
土岐市駅からほど近い住宅街にある細い路地を進むと、重山窯 金十製陶所が現れます。木村さんが生まれ育ったこの工場の一角には作品制作をする工房があり、電動ロクロや、蹴ロクロに取り外しのきく盤を付けた手廻しロクロが置かれています。また工房の反対側には、あらゆる方法で集められた釉薬の材料が所狭しと並んでいます。

木村さんの作品は、岐阜県南部・東濃地方の自然が育んだ素材を活かして作られています。焼き物の質感や色彩を追求する中で、自然の灰や地元で採れる土を使うことを重視しているそうです。
特に、酒器や花器のような一点物には、自ら山で土を掘り起こして精製することもあるそうです。灰についても、自宅の薪ストーブで燃やした灰や、地域で譲り受ける藁灰など、貴重な材料を集める努力を惜しみません。その熱意が、作品の独自性を支えています。
「僕が目指しているのは、土と釉薬の調和による独特の質感です。じわ~っと潤いを感じさせるようなしっとりした質感の焼き物が理想ですね」と木村さんは語ります。

焼きと釉薬に込める情熱、新たな表現への探求
木村さんは「焼き」にも強いこだわりを持っています。「土をしっかり焼き、ゆっくり釉薬を溶かしていく」ことを重視し、厚めのレンガを組んだ特注の窯を使用して、長時間じっくりと焼き上げる手法を採用。ガス窯の操作性を活かし、薪窯のような均一化しない複雑な環境に近づけて、簡略化する部分と手間を惜しまない部分を明確に分けて深みのある色合いを目指して焼成しています。
木村さんの制作過程は、まさに試行錯誤の連続です。自然の灰を使った灰釉は木の種類や部位によって性質が違うために、燃やした灰は毎回違うものとなります。「自然の素材を使う以上、同じように焼いても毎回結果が変わる」という言葉どおり、窯のわずかな温度差や、たった5分の焼成時間の違いで、釉薬の溶け具合や色合いは変わってしまいます。そのため原料作りから釉薬の調合には何度もテストを重ね、それでも匙加減が難しい繊細な作業となり、大変神経を使うそうです。

原料作りから始まり、釉薬調合、施釉、そして焼成へと続く作業は、「楽しみというよりも怖さを感じる」と木村さんは語ります。その理由は、結果が出るまで分からないため。窯の中は場所により温度も環境も違います。たとえテストが良くても、焼成中に何度も色味を確認しても、実際の作品になると思っていたものと違ったりもするそうです。「まるで三振かホームランかの勝負のよう」と木村さんは言います。安定させるために科学的な原料に置き換えることもできますが、それでは人工的な感じになってしまい、目指している質感が得られません。どんなに大変でも、釉薬の調合や窯の温度調整を繰り返し研究することで、新たな表現の可能性を模索し続けています。
興味も経験もゼロからのスタート、陶芸への葛藤と成長
木村さんが陶芸の道を選んだ背景には、家業に対する葛藤と決意がありました。大学卒業後は別の道を考えていましたが、「五代にわたって続いてきた家業を自分の代で終わらせたくない」という思いが芽生え、陶芸の世界に足を踏み入れることを決意しました。しかし、陶芸の経験もなく師匠もいなかった木村さんは、当初「何から手を付けていいかわからず、特に興味もないまま、ただ作業をこなしていた」と語ります。常にコンプレックスを感じながらの日々だったそうです。
そんな木村さんの転機となったのは、地元の展示施設で出会った桃山時代の“黄瀬戸”でした。その「表面から水がにじみ出るような、しっとりとした質感」に強く惹かれ、その質感を自分の作品で再現したいと強く思ったのです。
本格的に創作を志してから、木村さんは釉薬の質感にこだわるようになりました。釉薬の濃淡が映える形や、土ならではの素材感を活かした柔らかい造形を追求し、作品はシンプルな形から線や鎬(しのぎ)をいれたものへと進化していきます。本来のロクロ目を活かしながらも、線を入れることで凹凸に釉薬が溜まり、流れる様をより魅せることができるようになりました。「特に二重掛けの釉薬では、厚みや焼きの具合によって色や質感がまったく異なります。これは一点物ならではの魅力ですね」と語ります。

木村さんはそれをやる意味をとても大切にしています。それは「轆轤(ろくろ)で引くなら轆轤でやる意味、ロクロの良さが生きる形」、土の塊を刳り貫くなら、土の表情が生きる造形、電動ロクロと手廻しロクロの使い分けなど、それをやる意味をとても大切にしています。頭だけでなく手を動かしながら、何か気づきが出てこないか探っています。その中で生まれたのが完成した壺を縦にカットして皿に仕立てるという独創的なアイデアも形にしました。
美濃焼の伝統と革新:新たな可能性を追求する探求心
木村さんは、作品作りに取り組むだけでなく、地元の窯業や美濃焼全体の発展にも力を注いでいます。
「美濃焼には、伝統的な作品から分業制による大量生産品、また磁器や陶器など幅広い価格帯の多種多様な製品もあり、その方向性から美濃焼という業界全体を一つにくくるのは難しい部分があります。しかし、生まれ育った地で栄えた「美濃焼」という誇りを胸に、皆で助け合いながら、より良いものを作り続けていけたなら…」と木村さんは話します。手作りで美濃焼を制作する陶芸家としての顔と、量産品を扱う窯元の社長という二つの立場から、木村さんは地元の産業を支えているのです。
その思いは、木村さんの作品名にも表れています。「美濃」という名前をあえて使うのは、美濃焼への敬意と愛着の表れです。木村さんの代表的な作品には、古美濃(こみの)、瑠璃美濃(るりみの)、美濃斑(みのまだら)など、独自の名前が付けられています。
•古美濃(こみの)
木村さんの代名詞ともいえる作品で、黄瀬戸釉と鉄分を含む土を組み合わせています。遠目には鉄器のように見える重厚な色合いと質感が特徴です。
•瑠璃美濃(るりみの)
古美濃の釉薬と、コバルトを入れた瑠璃釉を重ねた作品で、下地の古美濃の濃淡によって黄色味が出たり、瑠璃釉が濃い部分では黒や瑠璃、溜まった部分に白っぽさが現れたりします。一つの作品で多彩な表情が楽しめる点が魅力です。
•美濃斑(みのまだら)
斑唐津(まだらからつ)に似た釉薬で藁灰を使用し、美濃の素材で仕上げた作品です。美濃斑はゆっくりじっくり焼き上げることにより、溶け始めた部分や流れ出した部分などが様々な層となり、立体感のあるしっとりとした質感が生まれます。
木村さんの作品は、土に含まれる鉄分量や土の粒子の違い、釉薬の使い方によってさまざまな表情を見せる、試行錯誤の末に生まれた完全オリジナルです。その探求心が、美濃焼の伝統と新たな可能性を両立させています。
美濃焼の未来を照らす情熱と希望
未来に向けて、木村さんは「質感」にさらなる深みを追求した作品作りを目指しています。
「まだ挑戦したいことが山ほどあります。自然の素材と向き合い、その魅力を引き出しながら、新しい形を生み出すことが僕の使命です」と語る木村さん。その言葉には、自らの限界を超えようとする情熱と覚悟が込められています。

かつて出会った桃山時代の『黄瀬戸』——その唯一無二の質感に衝撃を受けた瞬間の感動は、今も木村さんの創作の原点であり続けています。その譲れない理想に向かう執念は、土と火が織りなす表情豊かな作品に生命を吹き込みます。
木村さんの情熱は、美濃焼の伝統に新たな息吹を与えるとともに、その未来を切り開く希望の光です。そして、あの日感じた心震える感動を胸に抱きながら、彼の挑戦はこれからも止まることなく続いていくでしょう。
(2024年11月、インタビュー:志村 知夏)
information
重山窯 金十製陶所
〒509-5132 岐阜県土岐市泉町大富247-2