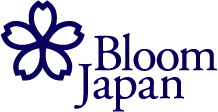深山窯 阪口浩史氏 インタビュー
「継続こそが力なり」の言葉を胸に師の教えを真摯に体現
プロフィール/陶歴
(さかぐち・ひろし)
1969年 岐阜県飛騨市神岡町生まれ。1989年 岐阜県立多治見工業高校 窯業専攻科卒業、深山窯・近田精治氏に師事。2005年に深山窯を継承、独立。阪神百貨店、小田急百貨店、松坂屋名古屋店、JR名古屋タカシマヤ、宮崎ギャラリー陶花などで個展を多数開催。2021年より美濃陶芸協会副会長。 日展会友 日本新工芸家連盟審議員
(受賞歴 2025年現在)
- 1989年
- 岐阜県産業教育振興会長賞受賞
- 1993年
- 日本新工芸展入選(以降7回)
- 1994年
- 美濃陶芸展 中日奨励賞受賞(以降3回)
- 1995年
- 日展 入選(以降20回)
- 1996年
- 日本新工芸展 新工芸奨励賞受賞
- 2002年
- 日本新工芸展入選作品を外務省が買い上げ
- 2007年
- 織部花器「清流」が美濃陶芸永年保存作品に選定される
- 2009年
- 美濃陶芸桔梗賞受賞
- 2010年
- 美濃陶芸展 美濃陶芸大賞受賞
- 2012年
- 美濃陶芸展 美濃陶芸大賞受賞
受賞作品 織部花器「想」が岐阜県現代陶芸美術館に収蔵される - 2014年
- 美濃陶芸展 美濃陶芸大賞受賞
受賞作品「爽風」がとうしん美濃陶芸美術館に収蔵される - 2015年
- 多治見市表彰(産業の振興に貢献)を受ける
- 2016年
- 第2回美濃陶磁育成智子賞受賞
- 2019年
- 日展東海展 中日賞受賞
岐阜県伝統文化継承功績者顕彰を受ける - 2021年
- 日本新工芸展 彫刻の森美術館賞受賞
美濃陶芸展 中日陶芸賞受賞 - 2022年
- 第40回卓男賞受賞
- 2023年
- 日本新工芸展 文部科学大臣賞受賞
美濃陶芸展 美濃陶芸大賞受賞
受賞作品 紅紫の器「実り」がとうしん美濃陶芸美術館に収蔵される
多治見に根ざす 深山窯の原点
岐阜県多治見市大薮町──交通量の多い国道から脇へ入った、緑豊かな丘陵地。なだらかなカーブを描く砂利道を進んだ先の広い敷地が、陶芸家・阪口浩史さんの工房『深山窯』です。庭先には、趣味が転じて半ば副業のようになった養蜂の巣箱が20近く並び、初夏の空中を舞う蜜蜂の大群が忙しく動き回っていました。工房内は手入れが行き届き、土間や轆轤場(ろくろば)でさえ埃っぽさがまるでありません。趣のある木製の建具や床、黒光りする重厚な梁が、歳月の積み重ねを感じさせます。


師匠・近田精治氏が建てた工房を、阪口さんが引き継いだのは、15年間にわたる師弟関係の後、今から20年ほど前のことです。多治見工業高校専攻科の教員でもあった陶芸家・近田氏との出会いが、阪口さんの陶芸家としての人生の始まりでした。
幼少期から図工などの物づくりが好きだった阪口さんは、“職人”という将来像を漠然と思い描いていたそうです。進路を考え始めた中学3年生の時、多治見工業高校の資料を偶然手にし、陶磁器の製造過程を学べる科があることを知って、「進学を即決した」と当時を振り返ります。「“窯業科”の漢字は読めなかったけれど」と笑っておっしゃいました。
15歳で親元を離れ、親戚宅に下宿しながら電車を乗り継ぎ、遠方から通学していたそうです。高校の3年間で陶磁器に関する知識と基礎技術に触れ、卒業後はさらに専門的な技術を身につけるため窯業専攻科へと進学します。「就職も考えたけれど、やっぱり諦められなかった」と阪口さん。日展に入選を重ねる実力者であった近田氏から、陶芸の基礎を学びました。
専攻科卒業後は近田氏に弟子入りしますが、実は承諾をいただいたのは2度目のお願いの時だったそうです。「先生は自分の本気度を試していたのかもしれない」と阪口さん。そして「弟子を取るということは人生を引き受けるということ。近田先生にも覚悟が必要だったのでは」とも。事実、それを機に近田氏は専攻科の教員を退職され、陶芸家としてのご自身のすべてを伝授すべく、その後15年間の日々を阪口さんと共にされるのです。

「一年後には個展を」陶芸家としての第一歩
それからの阪口さんの毎日は、近田氏の送迎に始まり、半日は土練りなど師の手伝いに、残りの半日は自身が轆轤に向き合い、夕方には清掃を終えて工房を出るという規則正しいものでした。「一に掃除、二に整理整頓」。工房を整えることは、土を触る以前の嗜みだという教えがあったそうです。作陶に使う小さな道具ひとつに至るまで“手入れ”を常とされていたことは、工房に一歩足を踏み入れた瞬間に容易に想像ができました。
近田氏はまた、身体を気遣うことも大切にされていたそうです。修業に入って間もないある日、指先に絆創膏を巻いていた阪口さんを見て、顔を見るよりも先に怪我に気付き、「それでは土が触れないじゃないか!」ときつく叱られたとのエピソードを、懐かしそうに話してくださいました。
師の「若いうちから技術を身に付け、公募展や個展に取り組むべき」との指針のもと、まずは1年後の個展を目標と定めたそうです。実際に阪口さんが21歳の時、故郷・飛騨市神岡町の公民館で初個展を開催し、その後は有名百貨店での数多くの個展へと続きます。さらに公募展での入選・受賞も年を重ねるごとに増えていきました。ご自身について「やり始めたら徹底的にやるタイプ」と語る阪口さん。師の教えに忠実に従い、真摯に向き合い続ける強い意志を感じました。

美濃焼の伝統をふまえながら 独自の釉薬の探求へ
「自分にしかできない作品を作るためには、伝統を踏まえ技術を身に付けることが必要」と阪口さん。
黄瀬戸のような肌合いに橙色の斑点が特徴の灰釉を中心に、織部や志野といった美濃の伝統的な釉薬を用いて作陶していた阪口さんですが、2015年ごろからは新たな試みで作品を手掛けてみえます。
「もともと赤が好きで、赤い釉薬をやりたかったけれど、“強い色”に迷いがあって手を出せなかった」そうです。一般的な銅を用いた“赤”は鮮やかな発色となり、「その赤じゃない」という思いがあったとも。作陶の中心であった灰釉に使用していた灰を使い切り、新たな原料が手に入らない状況のなか、“理想の赤”を求めて、専攻科の終了制作展で使用したクロム・スズピンク釉を応用するというアイデアに至ります。
流れるが故に色彩に変化が出やすい灰を主成分とした基礎釉に、酸化クロムと酸化錫(すず)を加えるのです。「高校時代から釉薬の調合はずっとやってきたから」と阪口さん。クロムの調合割合を変えることで、薄いピンクから紫がかった赤色へのグラデーションを表現できるようになり、その独自の釉薬に『紅紫(こうし)』と名付けました。長年の作家活動に加え、さらなる挑戦を続ける姿勢は高く評価され、『紅紫』の作品も深化を続けながら受賞を重ねていらっしゃいます。
作品を完成させる過程に付いて、阪口さんのこだわりを感じられるお話がありました。
公募展に一つの作品を応募する際には、同じ形で7〜8点を轆轤で挽くそうです。そして、その中で2番目に気に入った形から、窯に入れるとのこと。それは、微妙な形の違いによって釉薬が思ってもみない流れ方や発色をするため、それを確認するためなのだとか。「焼いてみるまでわからない」、それこそが陶芸の難しさであり、奥深さでもあるのです。
「自分は失敗していない、だからこそ研究した」
順風満帆に見える陶芸家人生にも、失敗や挫折がなかったわけではないのでしょうか?
阪口さんはおっしゃいます。「自分は失敗していない、だからこそ研究した」と。
その意味を説明してくださいました。以前は屋外の薪窯で定期的に“志野”を焼いていたそうですが、温度管理やタイミングが特に難しい薪窯の扱いも、近田先生の“焼き方レシピ”のおかげでうまくいっていたとのこと。つまり、師匠の存在が常にあったことは大きな学びであると同時に、失敗から学ぶ機会を失うことでもあったのです。「先ずは志野を“ガス窯で”焼く研究をして、何度も一窯丸ごと失敗し悔しい思いをした」と阪口さんは振り返ります。
近田先生が設計図を起こし、教え子たちと共にレンガを積んで拵えた薪窯。雨風にさらされ、経年劣化のため現在は使用できませんが、「いつか手直しして、また薪をくべたい」と阪口さんはおっしゃいました。

師匠とは
そして近田氏の存在とは
「厳しいことは言わず、ただひたすらに辛抱強く自分に接してくれた先生」に対し、「自分が良いと思った作品をダメと言われ、“此畜生!”と思うこともあった」と阪口さんは語ります。しかし、「先生に出会わなければ今の自分はいない」とも。15歳で単身多治見にやってきた青年が、厳しい世界に身を置きながらも続けてこられたのは、近田氏の存在があってこそなのです。
弟子に入って1週間も経たない頃、ふとした瞬間に先生が「お前、続けろよ」とおっしゃったそうです。「“はい”とすぐに返事をしてはいけないような、重い言葉な気がした」と阪口さん。返事もせず戸惑って立ち尽くしていると、「陶芸の世界でやっていくには、とにかく続けるしか方法はない」そして「継続は力なり、ではなく、継続こそ力なり」なのだと。この言葉は、阪口さんが陶芸を続ける原動力となっています。

目指すところは、“近田先生そのもの”
その人となりを伝えて
母校で指導をする現在、阪口さんが入学時の最初の授業で伝えるのは「手のケアと土の扱い」の2つ。指先を怪我しないよう保護すること。土を大切に扱い、無駄にしないこと。唯一近田先生が厳しかったことです。
阪口さんが授業で伝える内容のすべては、近田先生の言葉そのものです。「見よう見まねで知らず知らずのうちに身に付けてきたことを“言葉で”伝えなければならない・・・教えることは再認識のきっかけであり、勉強になる」と語ります。
そして卒業前の最後の授業で必ず伝えるのは「続けること」。
たとえ陶芸家の道を進まなくとも、土に触れ、轆轤を挽くことは続けてほしいと伝えているそうです。
ご自身を導いた師匠からの大切な言葉を伝えることは、陶芸家を育てると同時に、美濃焼の伝統を守ることにもつながっているように感じました。

(2025年4月、インタビュー:志村 知夏)
information
深山窯
〒507-0068
岐阜県多治見市大薮町296-1