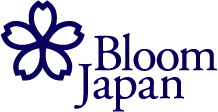半蔵窯 柴田育彦氏 インタビュー
美濃から世界へ発信。柴田育彦の器が結ぶ、心と心の交流
プロフィール/陶歴
(しばた いくひこ)
- 1956年
- 多治見市に生まれる
- 1978年
- 名城大学卒業
- 1987年
- 半蔵窯工房を開窯
- 1995年
- 公益財団法人美濃陶芸協会入会
- 1998年
- 人間国宝加藤孝造氏に師事
- 2003年
- 米国オハイオ州シンシナティ市にて陶壁制作
- 2006年
- 米国オハイオ州シンシナティ市にて個展開催
- 2007年
- 第13回庄六章茶盌展にて優秀賞受賞
- 2013年
- 米国シンシナティ市立美術館にて講演会
同市Funke Fired Artsにて陶芸講師(2013年~2019年) - 2014年
- 米国ボストン市に滞在し、作陶や陶芸指導を行う(以降継続)
- 2015年
- 米国シンシナティ市立美術館にて作品7点が収蔵される
- 2017年
- シンシナティ市・ボストン市にて陶芸講座
- 2019年
- シンシナティ市・ボストン市にて陶芸指導
高島屋大阪店にて個展(5回目) - 2020年
- ジェイアール名古屋タカシマヤにて個展
- 2023年
- 米国シンシナティ市立美術館にて講演
ジェイアール名古屋タカシマヤにて個展
多治見市ガレリア織部にて個展 - 2024年
- シンシナティ市にて陶芸講座・講演等
- 現在
- 岐阜、名古屋、東京、大阪などで多数の個展を開催
美濃陶芸協会理事
満足しきれない創作に挑み続ける
「いらっしゃい、どうぞ!」
小雨の中傘もささず、にこやかに外まで出迎えにいらしてくださった陶芸家 柴田育彦さん。
広い駐車場の奥、雨除けの下にはレンガで囲まれたドーム型の穴窯があり、薪が積まれています。
三角屋根に天窓が印象的な工房のガラス戸の前にはオブジェが置かれ、ウェルカムな雰囲気をかもし出しています。すぐ脇の芝草川という名のせせらぎに沿って工房の奥へと続くと、芝生の裏庭を眺めるに最適そうなリラックスチェアが並び、「いつもここで昼寝をしている」と笑って柴田さんはおっしゃいました。くつろげるスペースにすべく、少し前にDIYで軒先を広げられたとのこと。そのまま裏口から工房内へと案内して頂きました。
今年で30年になる柴田さんの工房『半蔵窯』。
経年変化が味わいを深めた柱や梁・天井の木材はあめ色に染み、吹き抜けが心地よい広い土間には小川からの風がよく抜けます。一段上がった板の間には柴田さんの作品がたくさん並び、奥には茶道の畳間と木の階段があります。ガラス製の入り口や壁・陳列棚はモダンな印象を与え、和の雰囲気のスペースのアクセントになっています。そして大きなスピーカーも。音響にもこだわっていらっしゃるそうです。

心地よい距離感で、温かなご縁を結ぶ
工房内を見渡すと、本棚には洋書が並び、ギャラリースペースの壁には外国人作家の作品もディスプレイしてあります。交流のある海外の陶芸家等から頂いたものだとか。柴田さんは20年以上も前から定期的にアメリカに赴き、現地の人々と陶芸を通した交流や活動を続けていらっしゃるのです。
きっかけは2002年、岐阜市との友好姉妹都市交流事業でオハイオ州シンシナティ市を訪れ、公園に設置するための陶壁のコラム(円柱の柱)を作成されたことです。国籍の異なる作家8人(中国、台湾、ウクライナ、ドイツ、フランス、ジンバブエ、アメリカ、日本)での作業は2か月に亘り、ホームステイでの滞在だったとのこと。そこで生まれた縁を大切に、そして広げ、現在に至るまでやり取りや行き来を繰り返しているそうです。
慣れない海外での長期滞在や、コミュニケーションにおける言葉の壁に、躊躇することはないのだろうか… そんな疑問はすぐに消え去りました。「絶対に失敗なんてしないよ、このぐらいで成功と思えば良いだけの事だから」とおっしゃる柴田さんの言動からは、挑戦することに対して不安や葛藤など微塵も感じられません。常に物事を前向きにとらえ、好奇心旺盛でいらっしゃるのです。「楽しまなきゃ損でしょ!」と柴田さん。目じりを下げて大きく笑われる柴田さんのフレンドリーでオープンな人柄には、国籍など関係なく誰もが親しみを感じることでしょう。「価値観が同じならどこの国の人とでもやっていけるよ」と、こぼれる笑顔でおっしゃいました。


損得を離れ、心満たす一器を届けたい
ご自身に付いて、「何か一つ良い事を述べるのであれば、人の為に何かするとき損得を考えないこと」とおっしゃる柴田さん。アメリカ滞在中には親しくなった友人宅にホームステイしながら、陶芸教室や講座、講演をこなすそうですが、寄付金を集めるためにボランティアで700個ものカップを創作し日本からアメリカに持ち込んだこともあるそうです。“良くしてもらう恩返しに”と、労力を惜しまない柴田さんの姿は、更なる友好の輪を生んでいることだろうと感じました。

『柴田育彦 作陶展』の真最中に行われた今回のインタビュー。
ギャラリーで拝見した個展作品についても伺いました。
展覧会の案内には、明るいコバルトブルーから藍色へのグラデーションの“青”と、黄色やオレンジにも近い“茶色”との縞模様が特徴の“鉢”が使われています。色を混ぜ合わせたところから「錦」、そして自由な発想が象徴の織部焼から「織部」を掛け合わせ、『錦織部』と名付けられた作品です。
釉薬から発想を得たという錦織部の作品には、大型の水差しや花器など様々な形がありますが、小ぶりな茶盌を手にした時、外観からの印象とは異なるその軽さに驚かされました。薄さ故だそうです。両面使用の台皿もあります。台面が太い縞模様・内側が円模様と凝ったデザインです。
柴田さんには、見る人・使う人を楽しませたいとの想いが常にあるそうです。ですが目指す作品の姿は、「斬新な目立つものではなく、平凡で普通だけど面白いもの」とも。伝統的な技法や素材で作られた美濃焼でありながら、どこかモダンでもありレトロでもある印象を与える錦織部の作品には、現代の日常生活でも使い易いようにとの配慮がうかがえます。
『金彩志野』と名付けられた鉢や茶盌・酒盃なども、小振りながら会場で存在感を放っていました。志野焼の白地に金彩を施した華やかな作品です。斜めに入った幾重ものラインや、ドット(水玉)模様にも見受けられる小さな連続した突起が金で彩られ、豪華で洗練された雰囲気でありながら新鮮な印象を与えています。陶芸において、通常であれば700℃を超えるガラスの焼成で金を施すそうですが、“焼かない”のが柴田さんのこだわりです。「焼く意味を感じないから」と、代わりに漆を使用する金継ぎの技法を用いることは、錆びることなく光沢感を残すための選択でもあります。
今回の個展のメインは『黒織部』であると柴田さんはおっしゃいました。ポスターにも使われている、新たな作風の『錦織部』ではないそうです。志野・黄瀬戸・瀬戸黒など、伝統的な美濃の焼物を作り続ける中で、「何か新しいものに挑むタイミングみたいなものがあって、やりたい時期が“今”来たんだよ」と柴田さん。「イメージがやっと頭の中でまとまった」とおっしゃいました。日頃より日常生活の何気ない“もの”から発想を得て、「轆轤ならどうやる!?」と考えを巡らせてもいらっしゃるそうです。
その例として、岩ガキやサザエをモチーフとしたユニークなデザインの作品を挙げてくださいました。絶妙なバランスで安定感を保った蓋の付いた入れ物です。お寿司屋さんで手にした貝の独特の形や質感を何とか作品に落とし込めないか…そう思った柴田さん、轆轤で成形し完成するまでに2年を費やしたそうです。高い好奇心と情報感度は新たなアイデアに繋がり、肯定的な思考・姿勢が作品完成へと導いているように感じました。

まるで山登り、、、登るほど景色が変わる終わりなき挑戦
これまで常に笑顔で、ご自身の経験や考えを面白おかしく語ってくださった柴田さんですが、長い陶芸家人生に付いてお聞きした際に印象的な言葉がありました。陶芸家とは「登山しているような感じ」だと。
20代後半で作陶を始め早40年、「あまり気負わず少しづつ作品制作をすればいい」と柴田さん。
しかしながら、この秋には渡米の予定があり、また幾つかの個展が来年に控えていらっしゃる柴田さん。すでに次の作品のデザインが頭の中にはあるそうです。また年内には、作陶の材料が置かれている裏庭スペースをDIYで改築する予定も。一階は物置スペース、二階は小部屋にするそうです。更に隣にもう一棟、茶室を拵えるという大掛かりな計画です。工房の二階スペースも整えたいし、水墨画にも磨きをかけたいし・・・日本人ならではの繊細な感性に基づく「アナログの美」、利便性を超えて器に込める日本の伝統文化を、使い手のもとへ届けたいという矜持――陶芸家としての柴田さんの精力的な活動は今後も続いていきます。

(2025年6月、インタビュー:志村 知夏)
information
半蔵窯
〒507-0813 岐阜県多治見市滝呂町6-70-1